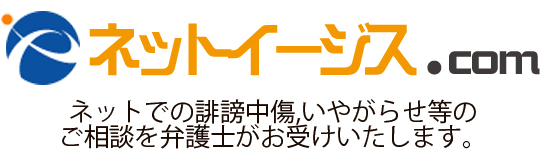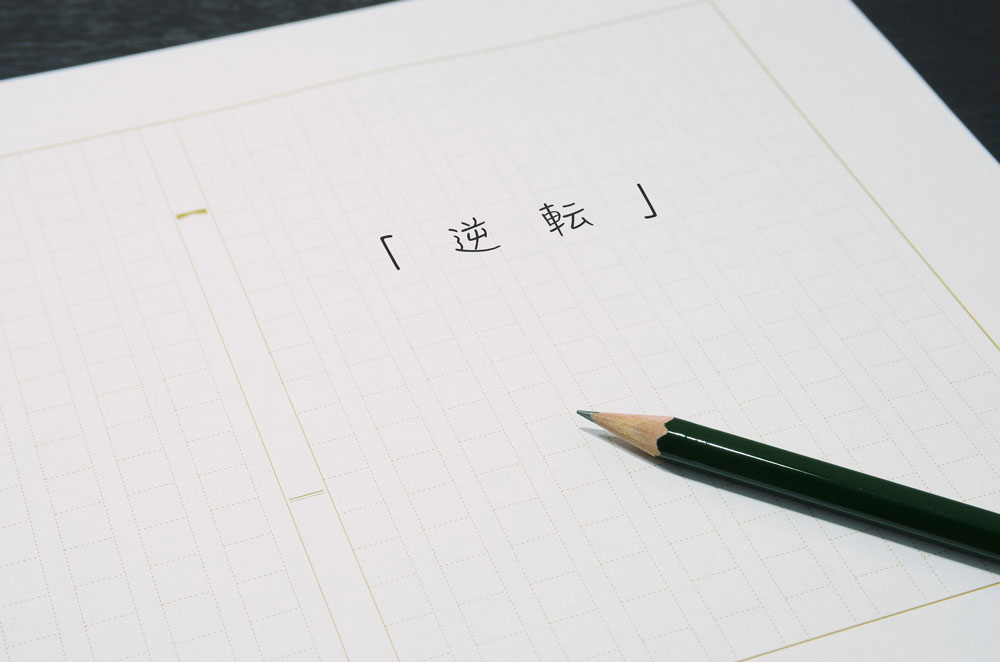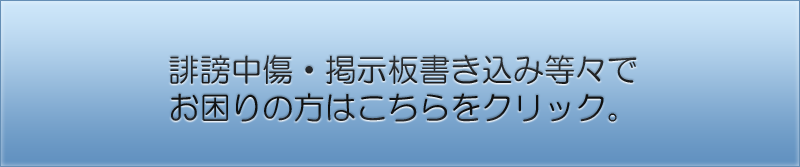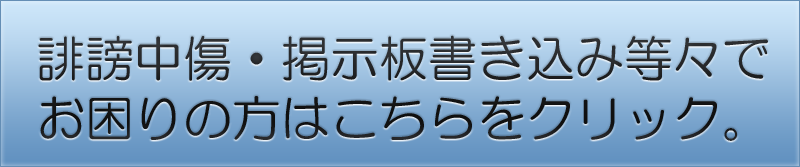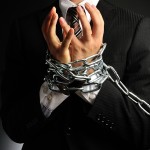裁判例からみるプライバシー権あれこれ2
裁判例2 最高裁判所平成6年2月8日判決(民集48巻2号149頁)「ノンフィクション『逆転』事件」
前回取り上げた「前科照会事件」に引き続き,似たような事例をご紹介します。 この裁判は,「ノンフィクション『逆転』事件」と呼ばれているものです。
アメリカ統治下の沖縄県で起きた傷害事件がノンフィクション作品として出版。
昭和39年(1964年)8月,アメリカ合衆国統治下の沖縄県宜野湾市で,甲野太郎さん(仮名)ら4名と,アメリカ軍兵士2名との間で口論・喧嘩が起きます。
この喧嘩で,アメリカ軍兵士のうち1名が死亡,もう1名が重傷を負いました。そのため,甲野さんは,傷害致死罪・傷害罪で起訴され,裁判所から懲役3年の実刑判決が言い渡されました(なお,傷害致死罪については無罪だが,そこに含まれる傷害の部分については有罪,(もう1名に対する)傷害罪については無罪,という判断となっています)。
当時,アメリカ合衆国統治下にあった沖縄県では「陪審員制」がとられており,甲野さんの裁判も陪審制でおこなわれました。
その裁判に陪審員として参加していた伊佐千尋氏が,陪審員としての体験に基づき著したのが「逆転」というノンフィクション作品であり,昭和52年(1977年)に新潮社から出版されました。
(岩波書店ウェブサイトより引用)
「1964年,アメリカ支配下の沖縄普天間でアメリカ兵殺傷事件が起きた.容疑者は沖縄の青年4人.裁判の陪審員を任じられた著者は,沖縄人に重罪を課そうとするアメリカ等の陪審員が多数を占める陪審審議で,ついに「逆転」を生じさせた.裁判のあり方をも考えさせる息づまる法廷記録.大宅壮一ノンフィクション賞受賞.」
引用元URL:http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/60/2/6030450.html
「逆転」では,甲野さんの実名が記載されており,甲野さんが事件を起こしたこと,懲役3年の実刑判決を受けたことが,読者に分かるようになっています。
ちなみに,控訴審の判決文では,「「はじめに」と題して,「本書に現れる人物には架空のキャラクターはいない。不明の米兵ひとりと陪審員を除けば,他の固有名詞を含めてみな実名である。」と記載されている。全体は,「第一部 被害者と加害者たち」,「第二部 裁判」,「第三部 陪審評議」,「第四部 判決」から成り」となっています。
「逆転」が出版された時点は,既に事件から13年が経過しており,甲野さんは沖縄を離れ,東京でバス運転手として働いており,結婚していました。
そして,甲野さんの周囲には,甲野さんが起こした事件や判決のことを知っていた人はいませんでした(と,裁判所は認定しています)。
甲野さんは,「逆転」によって前科が公表されたことで,勤務先を解雇されるのではないか,妻から離婚されるのではないかという不安を持ち,また,多くの人が自分の前科を知るところになり,多大な精神的苦痛を受けたとして,著者に損害賠償として300万円の支払いを求めました。
裁判所は,甲野さんの利益が侵害されたとして請求を認め,著者に損害賠償を命じた。
以下,詳しくみてみましょう。
上記のような甲野さんの訴えにつき,一審,控訴審はいずれも甲野さんの請求を認め,著者に50万円を支払うよう命じました。
そこで,「逆転」の著者は,「陪審制度の長所ないし民主的な意義を訴え,当時のアメリカ合衆国の沖縄統治の実態を明らかにしようとすることを目的としたものであり,そのために本件事件ないしは本件裁判の内容を正確に記述する必要があった」,「4名が無実であったことを明らかにしようとしたものであるから,本件事件ないしは本件裁判について,被上告人(筆者注:甲野さん)の実名を使用しても,その前科にかかわる事実を公表したことにはならない」などと主張し,実名を記載したことが甲野さんの権利(プライバシー)を侵害するものではないとして上告しました。
最高裁判所は,前回取り上げた「前科照会事件」を引用して,「ある者が刑事事件につき被疑者とされ,さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け,とりわけ有罪判決を受け,服役したという事実は,その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから,その者は,みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき,法的保護に値する利益を有する」とした上で,さらに,「その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては,一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから,その者は,前科等にかかわる事実の公表によって,新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有する」としました。
つまり,最高裁判所は,「前科等に関する事実を公表されないこと」と,「(前科等に関する事実の公表によって)社会生活の平穏を害されたり,更生を妨げられたりしないこと」を,法的に保護されるべき利益として認めました。
しかし,最高裁判所はそれにとどまらず,「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益」と,「前科等にかかわる事実につき,実名を使用して著作物で公表する必要性」を比較して,前者が優越する場合のみ,損害賠償を求めることができるとして,例外的に前科等の事実の公表が許される場合があることを認めたのです。
具体的には,最高裁判所は「事件それ自体を公表することに歴史的又は社会的な意義が認められるような場合には,事件の当事者についても,その実名を明らかにすることが許されないとはいえない」として,「ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは,その者のその後の生活状況のみならず,事件それ自体の歴史的又は社会的な意義,その当事者の重要性,その者の社会的活動及びその影響力について,その著作物の目的,性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので,その結果,前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には,その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない」としました。
そして,この事件の結論としては,「本件著作が刊行された当時,被上告人は,その前科にかかわる事実を公表されないことにつき法的保護に値する利益を有していたところ,本件著作において,上告人(筆者注:著者)が被上告人の実名を使用して右の事実を公表したことを正当とするまでの理由はないといわなければならない。そして,上告人が本件著作で被上告人の実名を使用すれば,その前科にかかわる事実を公表する結果になることは必至であって,実名使用の是非を上告人が判断し得なかったものとは解されないから,上告人は,被上告人に対する不法行為責任を免れない」として,著者の損害賠償責任を認めて上告を棄却しました。
ネット時代において,より深刻化する前科・犯罪についての情報による被害
最近では,犯罪報道がインターネット上で瞬く間に拡散されるというケースがままあります。
もとより,犯罪自体は憎むべき行為ですが,犯罪についての情報がいつまでも残っている(しかも,検索によって容易に探知できる)ということが,本人の更生に悪影響を及ぼしてしまうこともあるのではないでしょうか。
昨年(平成26年)5月には,欧州司法裁判所が,検索エンジンの検索結果に関して,検索エンジン運営者には,「EUデータ保護指令」(「個人データ取扱いに係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する1995年10 月24 日の欧州議会及び理事会の95/46/EC 指令」)で規定されている,「管理者」としての削除義務があるという判断を示しました(いわゆる「忘れられる権利」についての判断として,日本でも大きく報道されたので,目にされた方も多いかと思います)。
最近では,「デジタルタトゥー」という言葉があるように,前科・犯罪に関する情報に限らず,インターネット上に個人情報などが拡散され,これが半永久的に残ってしまうということの問題が指摘されています。
インターネット時代の課題として考えなければならないことだと思います。
※判決文に興味のある方は,裁判所ウェブサイトにてご覧ください。
→ http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/442/052442_hanrei.pdf