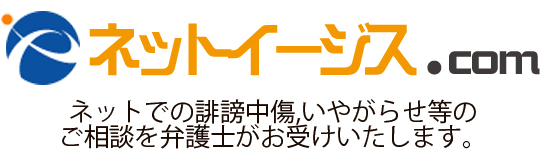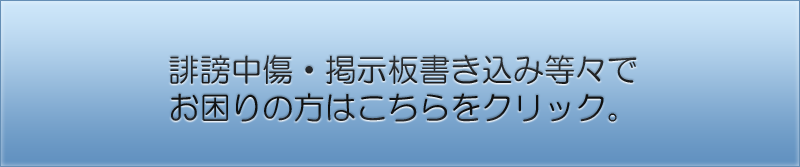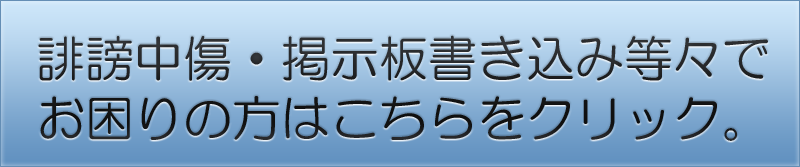社会的評価を低下させる表現が名誉毀損になる場合,ならない場合
少し前の話になりますが,今年の10月5日,橋下徹氏に関して書かれた週刊誌記事が名誉毀損等にあたるかどうかについて争われた裁判で,発行元の会社に275万円の支払いを命じる判決がなされた,という報道がありました(朝日新聞平成27年10月6日付「橋下市長の記事は名誉毀損,新潮社に賠償命令 大阪地裁」)。
記事によれば,「判決は内容が真実かどうかは判断せず,取り上げているのは私生活上の問題だと指摘。「(記事により)政治家としての資質に否定的な判断をする読者は相当多く,社会的評価を低下させる。公益を図る目的があったとはいえない」と判断した。」というものだったそうです。
名誉毀損とは
「名誉毀損」というのは,人(法人,団体なども含みます)の社会的評価を低下させるに足る内容を,不特定または多数に向けて発信(=公表)した場合に成立します。
ちなみに,刑法上の名誉毀損罪に該当するのは「事実」を公表した場合だけですが,民事上は,人の社会的評価を低下させるに足る表現であれば名誉毀損にあたります。
参考判例:最高裁平成9年9月9日民集51巻8号3804頁
問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである。
なお,上記判例に出てくる「事実」という単語ですが,これは,本当のこと,つまり「真実」という意味合いで用いられているものではなく,「意見ないし論評を表明するもの」との対比で用いられていることに注意が必要です。
具体例を挙げて説明すると,「Aくんは数学の中間試験で100点をとった」という表現は,「事実の摘示」にあたりますが,「Aくんは数学ができる」という表現は,ある事実(この場合は,数学の中間試験で100点だったこと)を前提として「意見ないし論評を表明するもの」にあたります。
このように,ある表現が「事実の摘示」であるのか,「意見ないし論評を表明するもの」であるのかを区分するのは,いずれにあたるかによって名誉毀損が正当化される場合の要件が異なるからです。
次でみてみましょう。
名誉毀損が正当化される場合
社会的評価を低下させる内容を公開した場合であっても,それが名誉毀損にならない(正当化される)場合があるのですが,具体的には以下のような場合です。
- 「事実摘示」型の場合:表現内容が,「公共の利害に関する事実」に係るものであり,かつ,表現の「目的が専ら公益を図ること」にあった場合で,「摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったとき」(または「真実と信じるに相当な理由があったとき」)
- 「意見ないし論評の表明」型の場合:表現内容が,「公共の利害に関する事実」に係るものであり,かつ,表現の「目的が専ら公益を図ること」にあった場合で,「意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったとき」(または「真実と信じるに相当な理由があったとき」)には,「人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないとき」
名誉毀損にあたる表現内容であっても,一定の要件を満たすときには正当化される(責任を負わない)という扱いがされているのは,「表現の自由」が極めて重要な価値を持つと考えられているからです(憲法学においては,「自己実現の価値」,「自己統治の価値」といった言葉で説明されています。なお,「憲法で保障されているから重要」なのではなく,「重要だから憲法(という最高法規)に規定して保障している」と考えないと,「憲法を変えれば保障しなくてよい」となってしまうので注意が必要です)。
橋下氏のケース
ここで橋下氏のケースに戻ってみると,大阪地裁は,週刊誌記事の内容が橋下氏の社会的評価を低下させるものと認定・判断(したがって,名誉毀損にあたる)した上で,「取り上げているのは私生活上の問題だと指摘」したと報道されています。
上述した,名誉毀損が正当化される場合の要件の第一は,「公共の利害に関する事実」かどうか,という点でした。
「公共の利害に関する事実」というのは,一般市民が関心を寄せるのが正当であると考えられる事項のことをいい,例えば,犯罪行為に関する事実などがこれにあたります「(刑法230条の2では,「・・・公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。」と規定されています)。」
また,「公益を図る目的があったとはいえない」ということで,第二の要件である「目的が専ら公益を図ること」についても否定されています(なお,「専ら」という部分については,実際には「主に」ということで少し緩めに考えられています)。
そして,「内容が真実であるかどうかは判断せず」という点ですが,名誉毀損が正当化されるためには,上述した要件の全てが満たされていないといけないので,そのうちひとつでも認められないということになれば,名誉毀損が成立し,損害賠償責任を負うことになります。
したがって,「名誉毀損が成立する」という判決をくだすにあたって,大阪地裁は,「公共の利害に関する事実ではない」,「公益を図る目的もない」と判断したので,「真実であるかどうか」という点については判断をしなかった(する必要がなかった)ということです(なお,ひとつでも要件が満たされていなければ名誉毀損が成立するので,理屈としては,「公共の利害に関する事実ではない」ということだけ判断して,残りの2つについては判断しない,という内容でもよいということになります)。