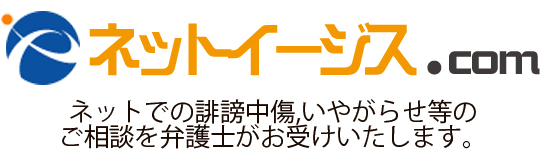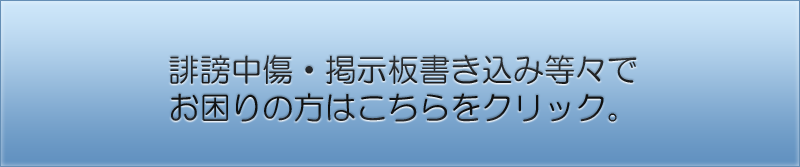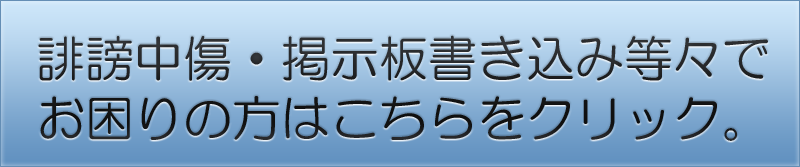真実だと思ったのに…。
先日のトピック「社会的評価を低下させる表現が名誉毀損になる場合,ならない場合」で,名誉毀損にあたる表現であっても,一定の要件を満たす場合には違法性が阻却され,法的責任が生じないことについて触れましたが,今回は,要件のひとつである「摘示した事実が真実であると信じるに相当な理由があったとき」について,少し詳しくご紹介しましょう。
名誉毀損の違法性が阻却されるには,「摘示した事実が真実であること」を証明する必要がありますが,真実であることを証明するには時として困難が伴います。
正当な表現行為であるにもかかわらず,「証明の失敗」によって責任が問われるということは望ましいことではないことから,最高裁判所は,昭和44年に出した判決において,「刑法二三〇ノ二の規定は,人格権としての個人の名誉の保護と,憲法二一条による正当な言論の保障との調和をはかつたものというべきであり,これら両者間の調和と均衡を考慮するならば,たとい刑法二三〇条ノ二第一項にいう事実が真実であることの証明がない場合でも,行為者がその事実を真実であると誤信し,その誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし相当の理由があるときは,犯罪の故意がなく,名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。これと異なり,右のような誤信があつたとしても,およそ事実が真実であることの証明がない以上名誉毀損の罪責を免れることがないとした当裁判所の前記判例(昭和三三年(あ)第二六九八号同三四年五月七日第一小法廷判決,刑集一三巻五号六四一頁)は,これを変更すべきものと認める。」(最判昭和44年6月25日刑集23巻7号975頁)と述べ,真実であることが証明できなかった場合でも,「真実であると誤信し,その誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし相当の理由があるとき」には,名誉毀損は成立しないとしました。
では,「確実な資料,根拠」とは,具体的にはどのようなものであればよいのでしょうか。
過去の裁判では,以下のような判断が示されています。
東京地判昭和47年5月15日判タ 279号292頁
「・・・ここでいう「確実な資料・根拠」とは,誤信の原因となつたそれを指称するのであるから,摘示事実の存在を証明するうえで,確実な証明力を備えているかどうかではなく,その資料・根拠が摘示事実の存在を証明するため一般に確実な手段として用いられる性質を具備しているかどうかを意味するとともに,その範囲も,職務上の権限をもち,それを豊富な専問的知識と経験に基づいて駆使しうる捜査機関が獲得できる資料・根拠であるかどうかを標準とするのは相当ではなく,常識ある一般人にとつて,真実であると確信するのが無理もないと認められる程度の資料・根拠であるかどうかをもつて判断の基準とするのが相当」
最判平成14年1月29日民集56巻1号185頁
「取材のための人的物的体制が整備され,一般的にはその報道内容に一定の信頼性を有しているとされる通信社からの配信記事であっても,我が国においては当該配信記事に摘示された事実の真実性について高い信頼性が確立しているということはできないのである。したがって,現時点においては,新聞社が通信社から配信を受けて自己の発行する新聞紙に掲載した記事が上記のような報道分野のものであり,これが他人の名誉を毀損する内容を有するものである場合には,当該掲載記事が上記のような通信社から配信された記事に基づくものであるとの一事をもってしては,記事を掲載した新聞社が当該配信記事に摘示された事実に確実な資料,根拠があるものと受け止め,同事実を真実と信じたことに無理からぬものがあるとまではいえないのであって,当該新聞社に同事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとは認められないというべきである。 」
最判平成22年3月15日刑集64巻2号1頁
「商業登記簿謄本,市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった者から受信したメール等の資料に基づいて,摘示した事実を真実であると誤信して本件表現行為を行った」,「・・・一方的立場から作成されたにすぎないものもあること,フランチャイズシステムについて記載された資料に対する被告人の理解が不正確であったこと,被告人が乙株式会社の関係者に事実関係を確認することも一切なかったことなどの事情が認められるというのである。以上の事実関係の下においては,被告人が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない」
最判平成23年4月28日民集65巻3号1499頁
「・・・新聞社が,通信社からの配信に基づき,自己の発行する新聞に記事を掲載した場合において,少なくとも,当該通信社と当該新聞社とが,記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性を有すると評価することができるときは,当該新聞社は,当該通信社を取材機関として利用し,取材を代行させたものとして,当該通信社の取材を当該新聞社の取材と同視することが相当であって,当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば,当該新聞社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り,当該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由があるというべき」
東京地判平成23年7月28日判タ1391号253頁
「被告が,その取材によって警察庁刑事局の幹部職員から得た情報については,その内容を虚偽であると疑うべき事情があったとはいえないことにかんがみれば,被告において,上記取材結果に加え,更なる裏付け取材をすることまで要求するのは相当でないというべきである。そうすると,被告において本件摘示事実を真実と信ずるについて相当の理由があったというべき」
これらの裁判例を前提にすると,「真実であると誤信し,その誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らし相当の理由がある」と認められるためのハードルは,相当に高いと言わざるを得ません。
あまりにハードルを高くしてしまうと,表現行為が必要以上に萎縮してしまうことになりますので,適切なバランスが求められるところであると思います。