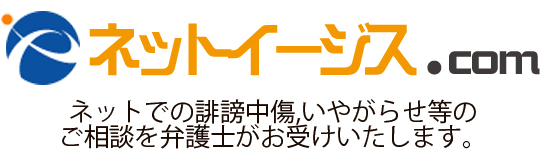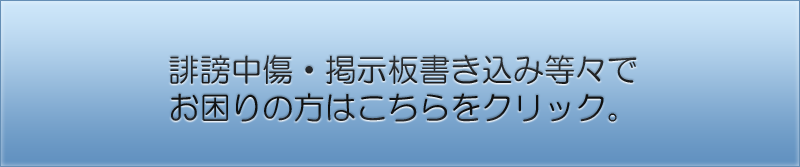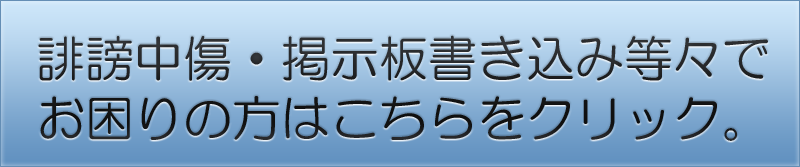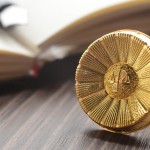最近の裁判例から:書籍「日本会議の研究」の差止め仮処分取消しについて
業務が立て込んでおり,久しぶりの更新となりました。
さて今回は,最近話題にのぼることの多い「日本会議」についての書籍「日本会議の研究」(菅野完,扶桑社新書)を巡る裁判について取り上げます。
「日本会議の研究」は平成28年4月に出版されましたが,この書籍の中で自分の活動について言及された男性が,その活動に関する虚偽の記述によって名誉を毀損されたとして,出版差止めを求めて東京地裁に仮処分命令の申立てをしました。
東京地裁は男性の申立てを認め,平成29年1月,男性についての記載のうち,虚偽と認められる部分を削除しなければ出版してはならないとする仮処分命令を決定(以下「第1次決定」といいます)しました(毎日新聞平成29年1月7日「ベストセラー「日本会議の研究」販売禁止の仮処分決定」など)。
第1次決定を受け,出版元である扶桑社は「虚偽である」とされた記述を削除した上で書籍の出版を続けていましたが,同時に,第1次決定は誤りだとして不服申立て(保全異議)をしていました。
そして今般,保全異議に関する判断がなされ,東京地裁は,出版差止めを認めた第1次決定は誤りであるとして,これを取り消すという決定(以下「第2次決定」といいます)をしました。
報道によれば,東京地裁は以下のように判断して差止めは認められないとしたようです。
産経新聞(http://www.sankei.com/affairs/news/170331/afr1703310047-n1.html)
「「記述が真実でないと断じるには疑念が残る上,公益を図る目的で執筆されたと認められる。社会的評判の低下の度合いも低い」などと指摘。出版差し止めが認められるほどの被害はないと判断した。」
時事通信(http://www.jiji.com/jc/article?k=2017033101382&g=soc)
「東京地裁は1月,同書に登場する男性に関する一部記述について,真実でない可能性が高いと指摘。名誉を傷つけられたとする男性の主張を認め,該当部分を削除しない限り販売を禁止するとしたが,31日の決定は「真実ではないことが明白と認めるのは困難」と判断した。」
さて,第1次決定と第2次決定とで,裁判所の判断が真逆になってしまった訳ですが,どうしてこのようなことになってしまったのでしょうか。
第1次決定をみてみると,上記毎日新聞記事によれば「決定はこの部分について「男性の社会的評価を低下させ,自殺者が出たことを裏付ける客観的資料はない。男性にも取材しておらず,真実でない蓋然(がいぜん)性がある」と判断した。」ということのようです。
ポイントは,太字にした「真実でない蓋然(がいぜん)性がある」というところです。
差止めを認めず,当初の仮処分命令を取り消した第2次決定では,これが「真実でないと断じるには疑念が残る」,「真実ではないことが明白と認めるのは困難」となっています。
一見したところ同じように見えますが,第1次決定の「真実でない蓋然(がいぜん)性がある」という表現は,(表現が)「真実であること」を出版元である扶桑社が証明しなければならない,という判断枠組みを前提にしているものと思われます。
一方,第2次決定の「真実でないと断じるには疑念が残る」あるいは「真実ではないことが明白と認めるのは困難」との表現は,「真実ではないこと」を仮処分を申し立てた男性の側が証明しなければならない,という判断枠組みを前提にしているものと思われます。
つまり,第1次決定の判断枠組みに従えば,「真実であること」の立証責任が扶桑社にあるので,(立証しきれずに)「真実であるかどうか,分からない」という状態にとどまった場合(や,より積極的に「真実でない可能性がある」と裁判官が考えた場合)は,扶桑社の負け(=差止めが認められる),ということになるのです。
一方,第2次決定の判断枠組みでは,「真実ではないこと(が明白)」の立証責任が男性にあるので,(立証しきれずに)「真実でないかどうか,分からない」という状態にとどまった場合(や,同様に「真実である可能性がある」と裁判官が考えた場合)は,男性の負け(=差止めが認められない),ということになるのです。
したがって,どちらの決定が採用した判断枠組みが妥当か,というところが問題となってくる訳ですが,だいぶ文章が長くなってきましたので,今回の記事はここまでにさせていただき,次回記事において考察をしたいと思います。