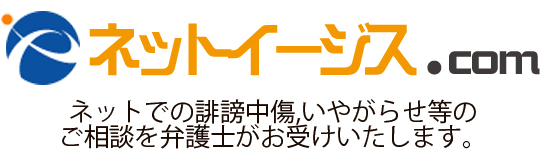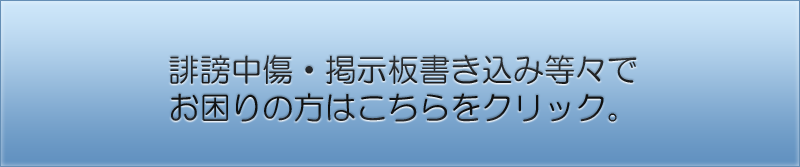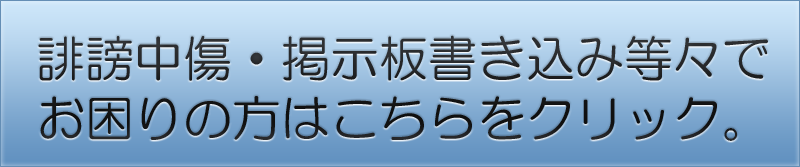ネットの書き込みを規制した国!違反すると罰金!?
実名を公開せず書込みが出来るインターネット。個人が気軽に情報発信することができ,様々な情報を手に入れることができるという反面,悪口やプライバシー情報が書き込まれたり,最近では「リベンジポルノ」といった問題もでてきました。時々テレビのニュースでも取り上げられますよね。
ニュージーランドでは,そうしたインターネット上に流通する「ネガティブ情報」を法律によって規制することを決めました。
詳しくは,こちらのBBCウェブサイト記事によれば,ニュージーランドの議会で,ネット上の有害情報を規制することを目的とした法律「有害デジタル通信法」(英文:”Harmful Digital Communications Act 2015”)が成立したそうです。
この法律では,個人に害をもたらすことを意図してネット上に情報を投稿した場合,
・投稿に用いられた言葉の酷さ(extremity)
・投稿の対象になった個人の年齢や性質(age and characteristics)
・ 匿名(anonymous)での投稿かどうか
・繰り返し(repeated)投稿されたかどうか
・投稿が伝播した範囲(extent of circulation)
・内容が真実かどうか(true or false)
・投稿された際の文脈(context))
といった要素を考慮して,その投稿が個人を害するものかどうかを裁判所が判断するという仕組みになっているようです。
そして,個人を害する投稿であると判断された場合,投稿者には,「2年以下の懲役または5万ニュージーランドドル(現在のレートで約400万円)以下の罰金」が科せられる可能性があります。
ちなみに,日本の刑法で規定されている名誉毀損罪の場合は,「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」となっていますから,ニュージーランドの場合は罰金が日本に比べてかなり高額となっていますね。
有害デジタル通信法が定める10原則
また,この法律では,「通信の原則」(Communication principles)として,以下の10原則が掲げられています(なお,和訳は私の仮訳であり,正式なものではありません)。
原則1(Principle 1)
デジタル通信は,個人に関するセンシティブ情報を公表するものであってはならない。
(A digital communication should not disclose sensitive personal facts about an individual.)
原則2(Principle 2)
デジタル通信は,脅迫的,威圧的,威嚇的であってはならない。
(A digital communication should not be threatening, intimidating, or menacing.)
原則3(Principle 3)
デジタル通信は,(それによって)影響を受ける立場にある人物に対して甚だしく攻撃的・不快なものであってはならない。
(A digital communication should not be grossly offensive to a reasonable person in the position of the affected individual.)
原則4(Principle 4)
デジタル通信は,低俗あるいは猥褻なものであってはならない。
(A digital communication should not be indecent or obscene.)
原則5(Principle 5)
デジタル通信は,個人に対するハラスメント(嫌がらせ)のために用いられてはならない。
(A digital communication should not be used to harass an individual.)
原則6(Principle 6)
デジタル通信は,虚偽の主張であってはならない。
(A digital communication should not make a false allegation.)
原則7(Principle 7)
デジタル通信は,信用に反して著されたものを含むものであってはならない。
(A digital communication should not contain a matter that is published in breach of confidence.)
原則8(Principle 8)
デジタル通信は,他人を害する目的のためにメッセージを送るよう個人を扇動するものであってはならない。
(A digital communication should not incite or encourage anyone to send a message to an individual for the purpose of causing harm to the individual.)
原則9(Principle 9)
デジタル通信は,自殺をするよう個人を扇動するものであってはならない。
(A digital communication should not incite or encourage an individual to commit suicide.)
原則10(Principle 10)
デジタル通信は,肌の色,人種,民族,出自,宗教,性別,性的指向,障害を理由として個人を侮辱するものであってはならない。
(A digital communication should not denigrate an individual by reason of his or her colour, race, ethnic or national origins, religion, gender, sexual orientation, or disability.)
政府機関や裁判所は,有害デジタル通信法に基いて行政を運営あるいは権限を行使するにあたり,上記の原則を考慮しなければならないとされていますので,「名誉毀損」や「侮辱」よりも広い範囲で表現行為が罰せられる可能性があります。
インターネット上に流通する情報について規制するニュージーランドの有害デジタル通信法ですが,悪意ある情報によって個人が傷つけられることは許されないことは当然のことながら,一方で,「表現の自由」に対する制約が,どのような目的で,どのような手段であれば許されるのか,非常に難しい問題をはらむものといえます。
行政機関や司法機関の運用が適切になされなければ,表現行為を不当に萎縮させることになってしまうでしょう。
なお,「元恋人への仕返し。リベンジポルノ問題。」で取り上げたように,日本では,昨年,いわゆる「リベンジポルノ法」(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)が制定され,名誉毀損やプライバシー侵害には該当しないようなケースでも,一定の要件を満たす場合には法律による対処が可能となりました。
インターネット上の悪意ある情報にお悩みの場合には,ひとりで抱え込まず,専門家に相談し,アドバイスを受けることをおすすめします。話をするだけでも,心の負担を軽くすることができると思います。
弁護士であれば,法的手続きを用いて記事の削除,投稿者の特定が可能です。初回相談は無料でお受けしていますので,インターネット上の問題でお困りのあなたのご相談をお待ちしています。