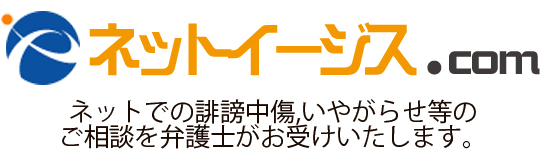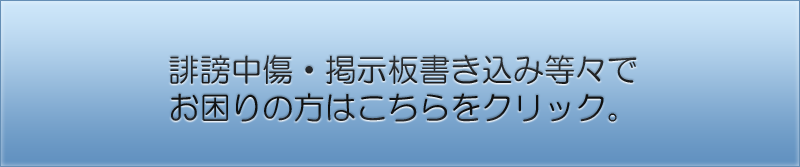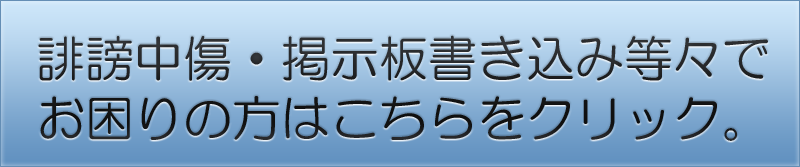日本の裁判史上初?「忘れられる権利」
以前,当トピックに投稿したエントリ「一度犯した罪は許されない?罪はいつまで背負うべき?」で,犯罪に関する報道記事(それを第三者がコピーアンドペーストしたものも含め)に対して,インターネット上でいつまでもアクセスが可能であることの問題性について考えてみました。
このときに取り上げたさいたま地方裁判所による仮処分命令に対しては,相手方グーグルが不服申立て(「保全異議」といいます)をしていたのですが,昨年12月22日,さいたま地裁の判断がくだされ,削除を認めた原決定の判断が維持(認可)されたそうです(東京新聞H28.2.28付記事「「忘れられる権利」初認定 逮捕歴の検索結果,さいたま地裁が削除決定」など)。
これまで,こうした犯罪に関する記事については,対象者が有する「新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益」を侵害するかどうかという観点から,「前科等にかかわる事実を公表されない法的利益」と,「前科等にかかわる事実につき,実名を使用して著作物で公表する必要性」とを比較して,前者のほうが優越する場合には前科等の公表が違法になるとされていました(最高裁判所平成6年2月8日判決(民集48巻2号149頁)「ノンフィクション『逆転』事件」)。
今回のさいたま地裁決定は,上記最高裁判決の示した「更生を妨げられない利益」から一歩進んで,「忘れられる権利」という概念を採用しました。
上記東京新聞記事によれば,さいたま地裁が示した判断基準は以下のようなものだったようです。
一,逮捕の報道があった人も更生を妨げられない利益がある
一,ある程度の期間の経過後は過去の犯罪を社会から「忘れられる権利」がある
一,ネットに逮捕情報が表示されると,情報を抹消して平穏な生活を送ることが困難なことを考慮し,検索結果の削除の是非を判断すべきだ
一,男性は逮捕歴が簡単に閲覧されるおそれがあり,その不利益は回復困難かつ重大
さいたま地裁は,なぜ従来の裁判例とは異なり,「忘れられる権利」という概念を用いたのでしょうか。
ひとつ考えられるのは,上記最高裁平成6年判決の示した基準は,「損害賠償請求ができるかどうか」が争われたケースにおけるものだったので,「差止め(削除)ができるかどうか」については判断していない,と考えることも可能です(これを,「判例の射程が及ばない」と表現します)。
また,差止めが認められるためには,何らかの「権利」に対する侵害が必要であり,「利益」(法律上保護される利益)に対する侵害では足りない(損害賠償によって被害回復を図れば足りる)である,という考え方もあるところです。
そうすると,さいたま地裁は,差止めを認めるには「更生を妨げられない利益」(の侵害)では不十分である,というように考えたのかもしれません(この点については,神田知宏弁護士のブログ記事「地裁決定が「忘れられる権利」に言及した理由の考察」が参考になります)。
なお,裁判所の仮処分命令によって出版物の印刷・頒布が禁止(事前差止め)されたことが違法かどうかが争われたケースで,最高裁が「人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である名誉を違法に侵害された者は(中略)人格権としての名誉権に基づき,加害者に対し,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることができるものと解するのが相当」と判示したものがあります(最高裁判所昭和61年6月11日判決民集40巻4号872頁)。
ただし,この最高裁昭和61年判決では,差止めが認められるためには「表現内容が真実でなく,又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて,かつ,被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるとき」という要件を満たさなければならないとされました。
そうすると,今回のさいたま地裁のケースのように,記事の内容(逮捕されたこと)そのものは真実である場合には,「表現内容が真実でなく」という要件を満たさない(また,新聞等のメディアによる報道である場合は「専ら公益を図る目的」も認められると考えられます)ことから,別の法的構成(=忘れられる権利)をとる必要があったといえます。
今後は,さいたま地裁の決定を足掛かりとして,「忘れられる権利」の具体的内容(対象となるのは犯罪に関する記事についてのみなのか,あるいは,それ以外であっても「平穏な社会生活を送ることを困難にさせる」と判断される事柄(ちなみに,EU司法裁判所が「忘れられる権利」に言及した判決で削除請求がされていたのは,自己が所有する不動産が競売にかけられたことを報道する過去(15年以上前)の新聞記事です)も含まれるのか),権利の発生を認めるための要件(さいたま地裁は,「ある程度の期間の経過後」と述べていますが,期間の経過だけなのか(どの程度の期間が経過すればよいのか),あるいは,その他の要素(例えば,犯罪であれば刑罰の軽重,犯罪態様等)も考慮すべきなのか)などについて,議論を積み重ねていく必要があるでしょう。